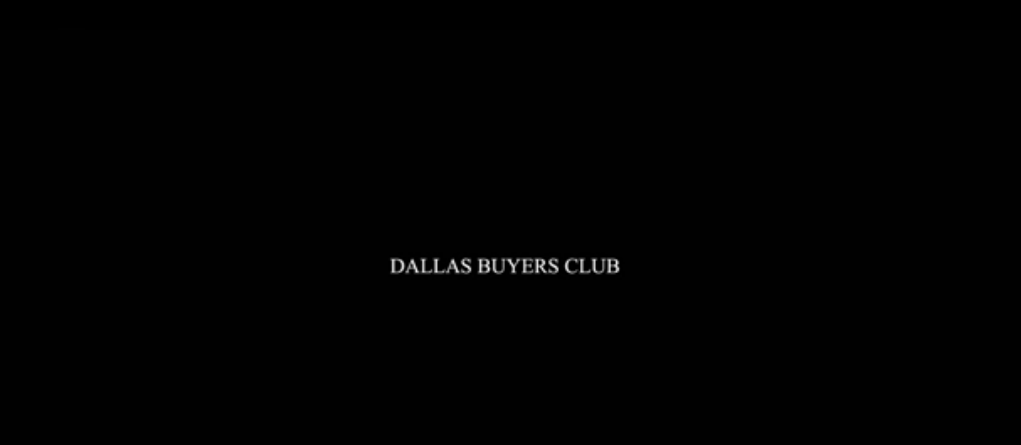ダラスバイヤーズクラブにみる、人類とHIVとの闘い
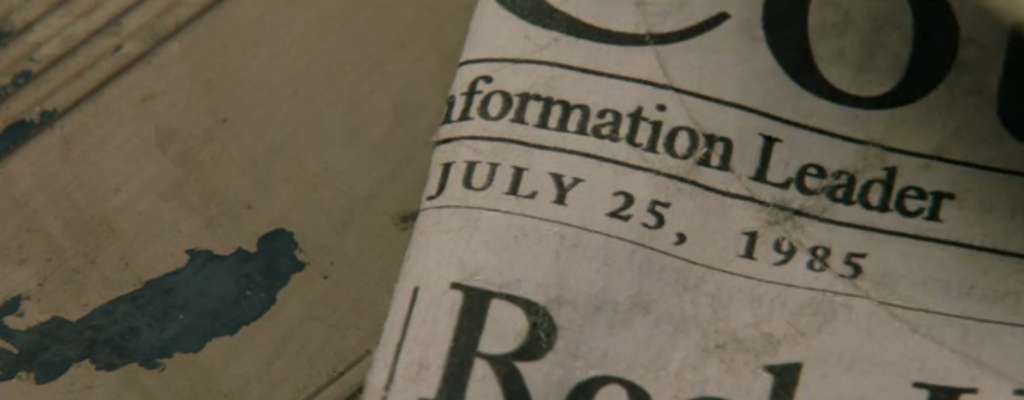
舞台は1985年のアメリカ、ダラス。
世界的にHIV感染者が増加し始め、エイズを発症し死に至る者も多かった時代。
今のように1日一粒の薬を飲むだけで、HIVの症状の進行を遅らせ、エイズを発症させることなく生涯を送ることが出来るようになる、そのずっと前の話。

カウボーイの主人公のロンは、酒と薬と博打と女に明け暮れ、日々荒れた生活を送っていたが、仕事中に気を失い、運び込まれた病院でHIVに感染していることが発覚する。

「あなたのT細胞の数値が9しかない、健康体ならば500-1500になる」
そして医師はロンが生きていることそのものが奇跡であり、余命は30日だと告げる。
タイトルからして退屈な映画だと誤解していたが、始めからかなり衝撃的な内容だ。

"17%が静脈注射のドラッグ使用者"
"避妊をしない性行為でも..."
HIVに関して調べ始めたロンは、自身が荒れた生活の中でドラッグ常用者の異性と避妊をせずに性行為をした過去を思い出す。
そして生きるために戦うことを決心し、彼の人生を賭けた戦いが始まっていくのだが。
この映画は、単にHIVに感染した一人の男のお涙頂戴の物語ではなく、1985年代当時のアメリカにおいて、HIV感染が絡むゲイへの偏見と、ロンのように感染した者に対する、周囲の人間の、その変わり様、そして、更には研究費が欲しい病院医師と製薬会社の思惑、アメリカのFDA(食品医薬品局)といった、個人を取り巻く利害関係者が織りなす人間模様を描いた社会派ドラマだ。

当時も今も、HIVそのものが深刻な問題であることに変わりはないが、当時は情報が断片的であり、例えば感染経路にしても、一般の人間からは感染者から触れられたり、唾をかけられただけで感染すると思われていた。(そういったシーンが描かれている)
ロン自身もまた偏見の塊。
差別主義者であり、ゲイへの偏見に満ちていながらも、彼は生きることへの執念から治療薬を得るため奔走する。
1985年当時は、HIV・エイズの有効な治療薬としてAZT(アジドチミジン)が数多く使用され、病院に入院した被験者もお金を払いながら投薬治療を受けていた。
ロンはAZTを入手するためにあの手この手を使い、病院の裏ルートから薬を入手することに成功する。

ロンはその偏見から、レイヨンを拒絶する。
後に2人は偏見の壁を越えて強い絆を築くのだが、そういった人間ドラマも丁寧に描かれている。
投薬効果からAZTは人体に有毒な薬品であることが分かり、ロンはFDA(食品医薬品局)の承認を受けていないHIVに有効な治療薬とされていた、ddC、ペプチドT、を、メキシコからの独自のルートで入手する。
当然ながら未承認薬であるため、アメリカへの持ち込みは禁じられており、ロンは手段を選ばず時には神父に変装し、FDA担当者の目をごまかす。
治療薬は自身のために使用するのはもちろんのこと、有効な治療薬を入手できない感染者にまで売買し、その資金でまた薬を購入しながら自身の治療も続ける。
次第に、HIV感染者として、薬の最大のマーケットは"ゲイ"であることに気付いたロンは、マーケットへ介入すべく、レイヨンと手を組む。
そして誕生するのが、映画のタイトルである、ダラスバイヤーズクラブだ。
ロンの当初の目的は、生きることそのものにあったが、次第に自身の使命に目覚め、多くの人間を救うため、薬の承認を巡ってFDAと争っていく。
この映画で最も美しいシーンは、差別主義者であり、ゲイへの偏見に満ちていたロン自身が、次第にレイヨンを受入れ、2人の間に見えない絆が結ばれた瞬間を描いたところ。

レイヨン演じる、ジャレット・レトの名演技が光る、この人間の微妙な心理を描いたところも見逃せない。

人間の本来あるべき姿を考えさせられるシーンだ。
そしてもう一つ、哀しむべきところは、ロンの担当医師であるイブへの想い。
HIV感染者は、たとえその命のともしびを消すことなく生涯を送ることが出来たとしても、やはり健常者との間には圧倒的な壁が立ちはだかる。
一度感染してしまうと二度と完治しない。
という点は現在も同じで、その絶望的なまでの事実がロンに突き付けられる。
イブとロンのデートシーンで、ロンは

「人間に戻った気分だ」
と話すが、その一言に、HIV感染者と健常者との間の大きな隔たりが込められている。
誰もが皆、口には出さぬが、HIV感染者に対して時に世間というものからは、
"人間ではない異質な存在"をみるような視線が向けられている事実を、本映画は指摘する。
そんな中でも、ロンは生きる権利を獲得するために必死で走り続けるが、いつしか本来の目的を見失ってしまう。

「死なないのに必死で 生きてる心地がしない」
ロンのような多くの人間の血が流れた今でも、この病気の根本の解決には至っていないが、現代の高度に発達した医療と世界各国の優秀な研究者の成果により、もはやHIVは死の病では無くなった。
それは、HIV感染者が「生きている実感」を得られるまでになったことを意味している。
だが足元には、名前すら持たない多くの人間の屍があることを忘れてはならない。
そういった視点から本映画は、HIV・エイズのこれまでの人類の戦いを紐解くものとして良作だ。
一方で不思議なのは、この物語には黒人が殆ど出てこない。
現在の医療はHIV感染を未然に防ぐ、PrEP(暴露前予防)の治療薬として Truvada(ツルバダ)が有効であると本ブログでも書いたが、やはりその費用は高額であり、恩恵を受けているのは一部の裕福な白人層で、貧しい層とされる黒人のHIV感染者にツルバダの入手は難しいという指摘もある。
まだまだ課題は山積みだ。
とはいえ、HIVという1つの病気について、様々な人種が絡み合う複雑な問題構造は、あまりにもアメリカ的であると感じる。
その複雑な問題構造をある視点からみる意味でも、本映画は面白い。